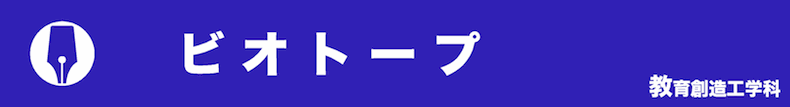| トンボ(蜻蛉)目 |
|---|
| 写真 | 種名 | 解説 |
|---|
 | クロスジギンヤンマ
Anax nigrofasciatus | ヤンマ科。腹長48-57mm。ギンヤンマに似ているが全体に黒っぽい。胸に二本の黒条がある。平地から低山地にかけての池沼に見られる。 |
 | オオシオカラトンボ
Orthetrum melania | トンボ科。腹長34mm。翅の付け根が黒いことでシオカラトンボとは区別できる。止水域で見られる。 |
 | シオカラトンボ
Orthetrum albistylum speciosum | トンボ科。腹長36mm。胸に黒条がある。止水域で見られる。 |
 | ハラビロトンボ
Lyriothemis pachygastra | トンボ科。腹長19-24mm。4月〜10月に池や湿地で見られる。 |
 | ショウジョウトンボ
Crocothemis servilia mariannae | トンボ科。腹長31mm。止水域で見られる。雌は黄色い。 |
 |
チョウトンボ
Rhyothemis fuliginosa |
トンボ科。腹長20-25mm。後翅が幅広く、蝶のようにひらひら飛ぶ。水草の多い池などに6月から9月に見られる。 |
 | ホソミイトトンボ
Aciagrion migratum | イトトンボ科。腹長24-32mm。池沼・湿地などで見られる。成虫越冬。体の大きさの割に腹部が細い。 |
 | アオモンイトトンボ
Ischnura senegalensis | イトトンボ科。腹長20-25mm。平地の池沼・湿地などで見られる。 |
 | ホソミオツネントンボ
Indolestes peregrinus | アオイトトンボ科。腹長30mm。平地や低山地の挺水植物がの多い池沼に生息する。成虫越冬。春になると体色が青くなる。 |
| カメムシ(半翅)目 |
|---|
| 写真 | 種名 | 解説 |
|---|
 | ナガメ
Eurydema rugosa | カメムシ科。体長7-9mm。アブラナ科の植物の汁を吸う。 |
 | ヒメナガメ
Eurydema dominulus | カメムシ科。体長6-8mm。アブラナ科の植物の汁を吸う。ナガメよりもやや小さく、暖かい地方に多い。 |
 | ルリクチブトカメムシ
Zicrona caerulea | カメムシ科。体長6-9mm。畑や雑草地に生息する。ハムシ類を好んで捕食する。 |
 |
イチモンジカメムシ
Piezodorus hybneri |
カメムシ科。体長9-11mm。マメ科の害虫として知られ、子実を吸汁する。背の中央の横筋は雄は白く雌は赤い。 |
 | マルカメムシ
Megacopta punctatissima | マルカメムシ科。体長5-6mm。草地によく見られる。マメ科の植物の汁を吸う。何十匹もの集団を作ることがある。 |
 | ホソヘリカメムシ
Riptortus clavatus | ホソヘリカメムシ科。体長14-17mm。ダイズなどを食害する。幼虫はアリそっくりで、擬態していると考えられる。 |
 | クモヘリカメムシ
Leptocorisa chinensis | ホソヘリカメムシ科。体長15-17mm。イネ科雑草が生えている草むらに多く見られ、しばしば稲を加害する。 |
 | ホオズキカメムシ
Acanthocoris sordidus | ヘリカメムシ科。体長14-17mm。ホオズキのほか様々な植物を食害する。 |
 | ホソハリカメムシ
Cletus punctiger | ヘリカメムシ科。体長8.5-11mm。イネ科雑草の穂先についていることが多い。 |
 |
ツマキヘリカメムシ
Hygia opaca |
ヘリカメムシ科。体長8-10mm。5-10月に出現する。荒地などで植物の茎から吸汁する。 |
 | アカヒメヘリカメムシ
Rhopalus macuratus | ヒメヘリカメムシ科。体長6-8mm。平地・山地の草原で普通に見られる。様々な植物につき、稲を加害することも多い。 |
 | ブチヒゲヘリカメムシ
Stictopleurus punctatonervosus | ヒメヘリカメムシ科。体長6-8mm。イネ科・タデ科・キク科など様々な植物につき、稲を加害することも多い。 |
 | ヒメジュウジナガカメムシ
Tropidothorax belogolowi | ナガカメムシ科。体長約8mm。花や果実の汁を吸う。 |
 | クロホシカメムシ
Pyrrhocoris sinuaticollis | ホシカメムシ科。体長9mm。地表の雑草や石の間に生息する。 |
 | トビイロサシガメ
Oncocephalus assimilis | サシガメ科。体長約15mm。前肢腿節が太い。 |
 |
シマサシガメ
Sphedanolestes impressicollis |
サシガメ科。体長13-16mm。肉食で、毛虫などの体液を吸う。 |
 | ナミアメンボ
Aquarius paludum | アメンボ科。体長オス11-14mm、メス13-16mm。全国の河川、湖沼に生息する。水面を滑って落下昆虫などを捕食する。 |
 | マツモムシ
Notonecta triguttata | マツモムシ科。体長11-14mm。池や沼などの水中で背中を下にして泳ぐ。捕食性で小魚やオタマジャクシ、虫などを捕らえて口吻を刺して唾液を注入し、体外消化をしながら吸収する。 |
 |
クマゼミ
Cryptotympana facialis |
セミ科。体長60-70mm。温暖な地域の平地や低山地に生息する。7月上旬から9月上旬に出現し、シャシャシャと鳴く。日本固有種。 |
 | アブラゼミ
Graptopsaltria nigrofuscata | セミ科。体長56-60mm。褐色の翅をもつ大型の蝉。成虫は7月から9月上旬に多く発生する。ジージーと鳴く。 |
 | ツクツクボウシ
Meimuna opalifera | セミ科。体長40-47mm。東アジアに広く分布する。成虫は晩夏から初秋に多く発生する。ツクツクボーシと鳴く。 |
 | アオバハゴロモ
Geosha distinctissima | アオバハゴロモ科。体長5.5-7mm。薄緑色の幅の広い三角形の翅を持つ。植物の細い茎に止まっていることが多い。 |
 | ソラマメヒゲナガアブラムシ
Megoura crassicauda | アブラムシ科。体長2.5mm。カラスノエンドウなどソラマメ類に集まり汁を吸う。体色は緑で脚・触角・角状管は黒。 |
 | セイタカアワダチソウヒゲナガアブラムシ
Uroleucon nigrotuberculatum | アブラムシ科。体長2.5mm。北米原産の外来種。セイタカアワダチソウに集まり汁を吸う。体色は赤で脚・触角・角状管は黒。 |