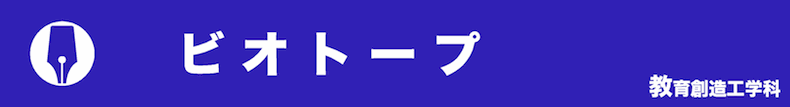| バッタ(直翅)目 |
|---|
| 写真 | 種名 | 解説 |
|---|
 | ニシキリギリス
Gampsocleis buergeri | キリギリス科。体長雄29-37mm、雌30-40mm。緑色または淡褐色。草地に住む。肉食性が強く、他の虫を捕らえて食べる。 |
 | ホシササキリ
Conocephalus maculatus | キリギリス科。体長13-17mm。緑色または褐色。草原・荒れ地に住む。イネ科植物を食草とする。 |
 | ヒメクダマキモドキ
Phaulula macilenta | ツユムシ科。体長30mm。樹上性。葉・花・花粉などを食べる。 |
 | ハラオカメコオロギ
Loxoblemmus campestris | コオロギ科。体長雄14-15mm、雌12-15mm。明るい草地に普通に生息する。リリリリと5-6声を区切って鳴く。 |
 | カンタン
Oecanthus longicauda | マツムシ科。体長14-18mm。林縁の低木上や草地に住む。ルルルルルと鳴く。 |
 | シバスズ
Polionemobius mikado | ヒバリモドキ科。体長雄6.1m、雌6.6mm。明るく丈の低い草地に生息する。ジーと長く鳴く。年1~2化で夏から秋に成虫になる。 |
 | オンブバッタ
Atractomorpha lata | オンブバッタ科。体長雄25mm、雌42mm。体色は緑色ないし褐色。草地に住む。広葉の草本を好んで食べる。 |
 | ショウリョウバッタ
Acrida cinerea | バッタ科。体長雄45mm、雌80mm。体色は緑色ないし褐色。草地に住む。 |
 | ショウリョウバッタモドキ
Gonista bicolor | バッタ科。体長雄27-35mm、雌45-57mm。体は細長くて直線状。頭は三角に尖る。イネ科の草地に住む。 |
 | トノサマバッタ
Locusta migratoria | バッタ科。体長35-65mm。日本のバッタでは最大。開けた場所に住む。 |
 | マダラバッタ
Locusta migratoria | バッタ科。体長雄30mm、雌35mm。翅の付け根に目立つ黄白色のすじがある。畑地に住む。 |
 | ツマグロバッタ
Stethophyma magister | バッタ科。体長は雄35mm、雌45mm。翅端と後脛節が黒い。山間部の草原などに生息する。後脚の踵部分で翅を蹴って発音する。 |
 | イボバッタ
Trilophidia japonica | バッタ科。体長18-35mm。日本のトノサマバッタ類では最小。開けた場所の地上に住む。 |
 |
ツチイナゴ
Patanga japonica |
イナゴ科。体長50-60mm。草の良く茂った野原に生息する。成虫で越冬する。 |
 | トゲヒシバッタ
Criotettix japonicus | ヒシバッタ科。体長は雄17mm、雌19mm。休耕田などの湿地に住む。カエルに襲われると、後脚を体から垂直に突き出す形にして硬直し、簡単には飲み込まれないようにする習性がある。 |
 | ハラヒシバッタ
Tetrix japonica | ヒシバッタ科。体長は5-10mm。休耕田などの湿気の多い場所に住む。翅は短くほとんど飛ばないが、はねる力は強い。背中の斑紋には変異が多い。 |
| チョウ(鱗翅)目 |
|---|
| 写真 | 種名 | 解説 |
|---|
 |
イモキバガ
Helcystogramma triannulellum |
キバガ科。開張15mm。幼虫がヒルガオやサツマイモの葉を曲げて巣を作り、内側から食害する。 |
 | シラホシトリバ
Deuterocopus albipunctatus | トリバガ科。前翅長5mm。幼虫はブドウ科植物の葉を食べる。 |
 |
カノコガ
Amata fortunei |
ヒトリガ科。昼行性で様々な花から吸蜜する。幼虫の食草はシロツメクサやタンポポなど。 |
 | トビイロスズメ
Clanis bilineata tsingtauica | スズメガ科。前翅長40mm。7-8月ごろ灯火によく飛来する。幼虫はマメ科植物の葉を食べる。 |
 |
ホシヒメホウジャク
Neogurelca himachala |
スズメガ科。開張35-40mm。昼間飛び回り、空中にとまって花から吸蜜する。成虫は6-11月に出現する。 |
 | ベニシジミ
Lycaena phlaeas daimio | シジミチョウ科。前翅長13-19mm。幼虫はスイバやギシギシの葉を食べる。季節型があり、夏は翅が黒っぽくなる。 |
 | ツバメシジミ
Everes argiades | シジミチョウ科。前翅長13mm。雄は翅の表が青いが、雌は黒い。幼虫はマメ科の植物の蕾を食べる。 |
 | ヤマトシジミ
Zizeeria maha | シジミチョウ科。前翅長13mm。本州以南に分布。雄は翅の表が青いが、雌は黒い。幼虫はカタバミの葉を食べる。 |
 | ウラギンシジミ
Curetus acuta | シジミチョウ科。前翅長19-27mm。表面には雄は朱色の紋、雌は水色の紋がある。幼虫はマメ科植物の花や蕾を食べる。 |
 |
キタキチョウ
Eurema mandarina |
シロチョウ科。前羽長20-27mm。草原や畑などでよく見られる。幼虫はマメ科植物の葉を食べる。 |
 | モンシロチョウ
Pieris rapae crucivora | シロチョウ科。前翅長28mm。幼虫はアブラナ科の植物の葉を食べる。 |
 | モンキチョウ
Colias erate | シロチョウ科。前翅長23-26mm。オスの翅は黄色だが、メスの翅は黄色と白の二種類がある。幼虫はマメ科の植物を食草とする。 |
 | ツマキチョウ
Anthocharis scolymus | シロチョウ科。前翅長20-30mm。年一化で3-5月に成虫が現れる。幼虫はタネツケバナ、ハタザオなどを食べる。 |
 | ナミアゲハ
Papilio xuthus | アゲハチョウ科。前翅長40-60mm。季節により大きさはかなり異なる。幼虫はミカン科の植物の葉を食べる。 |
 | ナガサキアゲハ
Papilio memnon | アゲハチョウ科。前翅長60-80mm。普通は後翅に尾状突起がない。幼虫はミカン科の植物の葉を食べる。 |
 | ツマグロヒョウモン
Argyreus hyperbius | タテハチョウ科。前翅長27-38mm。野原や公園でよく見られる。幼虫はスミレを食草とする。オスには前翅の白黒の斑紋がない。 |
 | コミスジ
Neptis sappho | タテハチョウ科。前翅長23-31mm。幼虫はマメ科植物を食草とする。普通は翅を開いて止まる。 |
 | ヒメアカタテハ
Cynthia cardui | タテハチョウ科。前翅長30mm。幼虫はヨモギなどを食草とする。長距離を移動することがある。 |
 | キタテハ
Polygonia c-aureum | タテハチョウ科。前翅長22-34mm。幼虫は食草のカナムグラの葉を綴って巣を作る。 |
 | タテハモドキ
Junonia almana | タテハチョウ科。幼虫はイワダレソウ・オギノツメなどを食草とする。日本では南西諸島に分布していたが、近年北上し九州全体に定着している。 |
 |
ヒメジャノメ
Mycalesus gotama |
タテハチョウ科。やや明るい林に生息する。腐った果実や獣糞を吸汁する。幼虫はイネ科植物の葉を食べる。 |
 | ヒメウラナミジャノメ
Ypthima argus | タテハチョウ科。前翅長18mm。幼虫はイネ科の植物を食草とする。多化性。 |
 | イチモンジセセリ
Parnara guttata | セセリチョウ科。前翅長20mm。幼虫はイネ科の植物を食草とする。多化性。長距離移動をすることがある。 |
 | コチャバネセセリ
Thoressa varia | セセリチョウ科。前翅長14-19mm。幼虫は竹笹類を食草とする。幼虫は葉を表面を内側に巻いて巣を作り、巣を食べて成長する。新しい巣を作る際には古い巣を切り落としてから移動する。 |