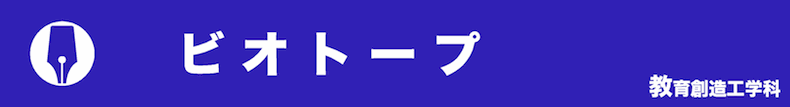| 甲虫(鞘翅)目 |
|---|
| 写真 | 種名 | 解説 |
|---|
 | ミイデラゴミムシ
Pheropsophus jessoensis | ホソクビゴミムシ科。体長15mm。日本では北海道から奄美大島までに分布する。外敵の攻撃を受けると、悪臭のあるガスを噴出する。 |
 |
ラミーカミキリ
Paragienea fortunei |
カミキリムシ科。体長10-20mm。カラムシやヤブマオなどを食草とする。5-8月に成虫が出現する。 |
 | カブトムシ
Trypoxylus dichotomus | コガネムシ科。体長30-54mm。オスの成虫の頭部に大きな角がある。幼虫は腐植土を食べる。 |
 | セマダラコガネ
Exomala orientalis | コガネムシ科。体長11mm。広葉樹の葉を食べる。 |
 | マメコガネ
Popillia japonica | コガネムシ科。体長8-15mm。成虫は夏から秋にかけて出現し、多様な植物の花や葉を食べる。 |
 | シロテンハナムグリ
Protaetia orientalis | コガネムシ科。体長21mm。樹液や熟した果実に集まる。花にも来る。 |
 | ヒゲナガハナノミ
Paralichas pectinatus | ナガハナノミ科。体長8-12mm。触角はオスはくし状になるが、メスは糸状。幼虫は水棲。 |
 | マメハンミョウ
Epicauta gorhami | ツチハンミョウ科。体長20mm。成虫は7-8月に出現し、豆類の葉を摂食する。幼虫はバッタの卵塊を摂食する。体液には毒性の強いカンタリジンが含まれる。 |
 | キマワリ
Plesiophthalmus nigrocyaneus | ゴミムシダマシ科。体長16-20mm。幼虫・成虫ともに朽木を食べる。広葉樹林の樹木や枯れ木にとまっているところをよく見かける。 |
 |
ウリハムシ
Aulacophora indica |
ハムシ科。幼虫はウリ科植物の根を食べ、成虫はウリ科植物の葉を食べる。 |
 | クロウリハムシ
Aulacophora nigripennis | ハムシ科。体長6-7mm。食草はウリ類。成虫は葉、幼虫は根を食べる。成虫が葉を食べる時、食べる部位の周囲に円く溝を掘る習性がある。 |
 | ヨモギハムシ
Chrysolina aurichalcea | ハムシ科。体長8.5mm。食草はヨモギ。青黒色のものと金銅色のものが混在する。久工大ビオトープでは青黒色の個体が圧倒的に多い。 |
 | アオバネサルハムシ
Basilepta fulvipes | ハムシ科。体長3-4mm。ヨモギなどキク科植物を食草とする。 |
 | スイバトビハムシ
Mantura clavareaui | ハムシ科。体長2-2.5mm。スイバやギシギシを食草とする。 |
 |
ヨツモンカメノコハムシ
Laccoptera nepalensis |
ハムシ科。幼虫・成虫ともにヒルガオ科のノアサガオやサツマイモなどを寄主植物とする。沖縄本島以南の南西諸島に分布していたが近年北上し、現在は九州全域に分布している。 |
 | ハイイロゲンゴロウ
Eretes sticticus | ゲンゴロウ科。体長10-16.5mm。荒れ地の水たまり、池などに普通に見られる。 |
 | ヒメガムシ
Sternolophus rufipes | ガムシ科。体長9-12mm。平地の池沼・水田などに見られる。 |
 | ナミテントウ
Harmonia axyridis | テントウムシ科。体長6.5mm。アブラムシ類を食べる。斑紋に変異が多い。 |
 | ナナホシテントウ
Coccinella septempunctata | テントウムシ科。体長7mm。アブラムシ類を食べる。 |
 | ヒメカメノコテントウ
Propylea japonica | テントウムシ科。体長3-4.6mm。アブラムシ類を食べる。 |
| ハチ(膜翅)目 |
|---|
| 写真 | 種名 | 解説 |
|---|
 | ハグロハバチ
Allantus luctifer | ハバチ科。体長20mm。幼虫はギシギシの葉を食べる。また、静止する時は丸くなる。 |
 | コガタスズメバチ
Vespa analis | スズメバチ科。働き蜂の体長22-28mm。昆虫を餌とする。木の枝、植え込み、軒下等の開放空間に巣を作る。 |
 | セグロアシナガバチ
Polistes jadwigae | スズメバチ科。体長20-26mm。日本産アシナガバチでは最大の種類。平地・市街地に普通に生息する。 |
 | コアシナガバチ
Polistes snelleni | スズメバチ科。体長11-17mm。山地に多く、民家にも巣を作る。 |
 | スズバチ
Eumenes decorata | スズメバチ科。体長18-30mm。泥で鈴のような形をした壺状の巣を作る。 |
 |
オオフタオビドロバチ
Anterhynchium flavomarginatum |
ドロバチ科。体長10-21mm。竹筒に泥で仕切りを作り営巣する。幼虫の餌としてイモムシなどを狩る。5-10月に成虫が出現する。 |
 |
サトジガバチ
Ammophila sabulosa |
アナバチ科。体長17-27mm。地中に巣を作り、イモムシを狩って幼虫の餌にする。 |
 | セイヨウミツバチ
Apis mellifera | ミツバチ科。体長10-13mm。腹部の前方が橙色をしており、この部分が黒っぽい日本ミツバチと見分けることができる。花の蜜を集めて巣に蓄え、蜂蜜を作る。外来種。 |
 |
キムネクマバチ
Xylocopa appendiculata |
ミツバチ科。体長18-25mm。胸部の毛が黄色く、他は黒色。花蜜や花粉を餌とする。母親が羽化後の子に餌を運ぶ行動が見られる(亜社会性)。 |
 |
クロバネセイボウ
Chrysis angolensis |
セイボウ科。ドロバチなどの巣に寄生する。 |